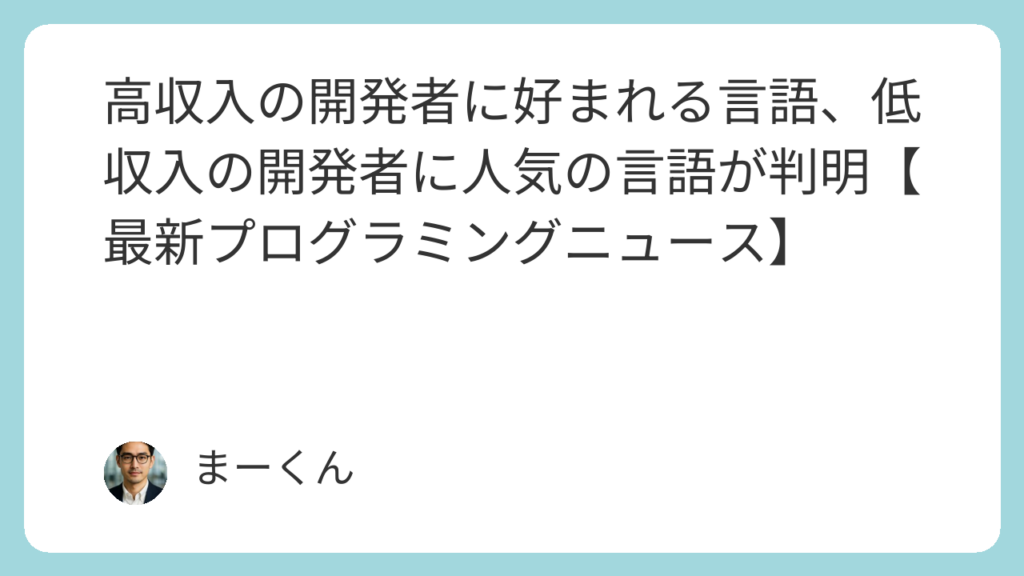 最新情報
最新情報 高収入の開発者に好まれる言語、低収入の開発者に人気の言語が判明【最新プログラミングニュース】
高収入の開発者に好まれる言語、低収入の開発者に人気の言語が判明【最新プログラミングニュース】世界中の開発者動向を追跡する「SlashData」が、最新の調査結果を発表しました。本記事では、高収入エンジニアが使う言語と、低収入層に多い言語がどれなのかをデータに基づいて解説します。これからプログラミング...
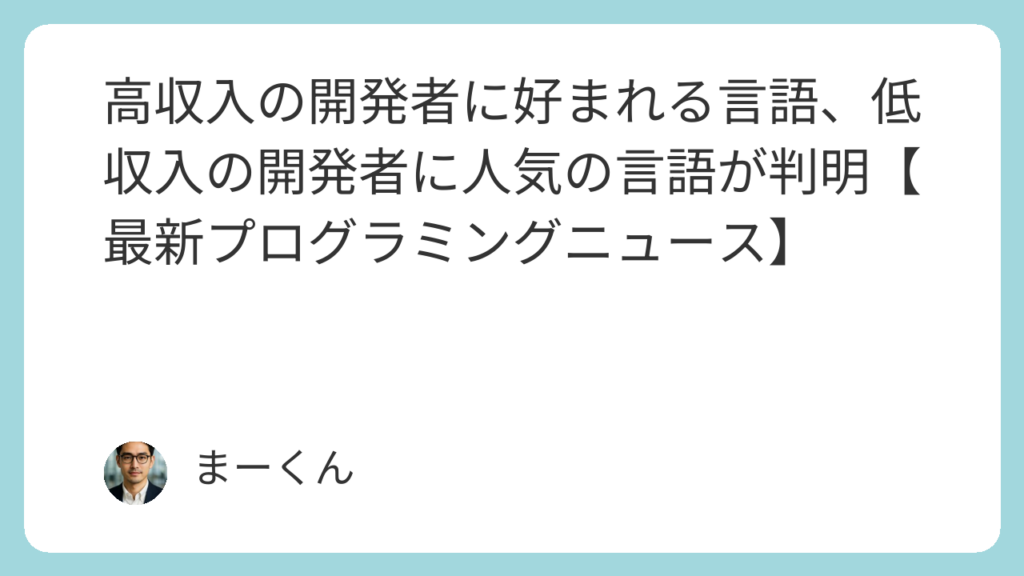 最新情報
最新情報 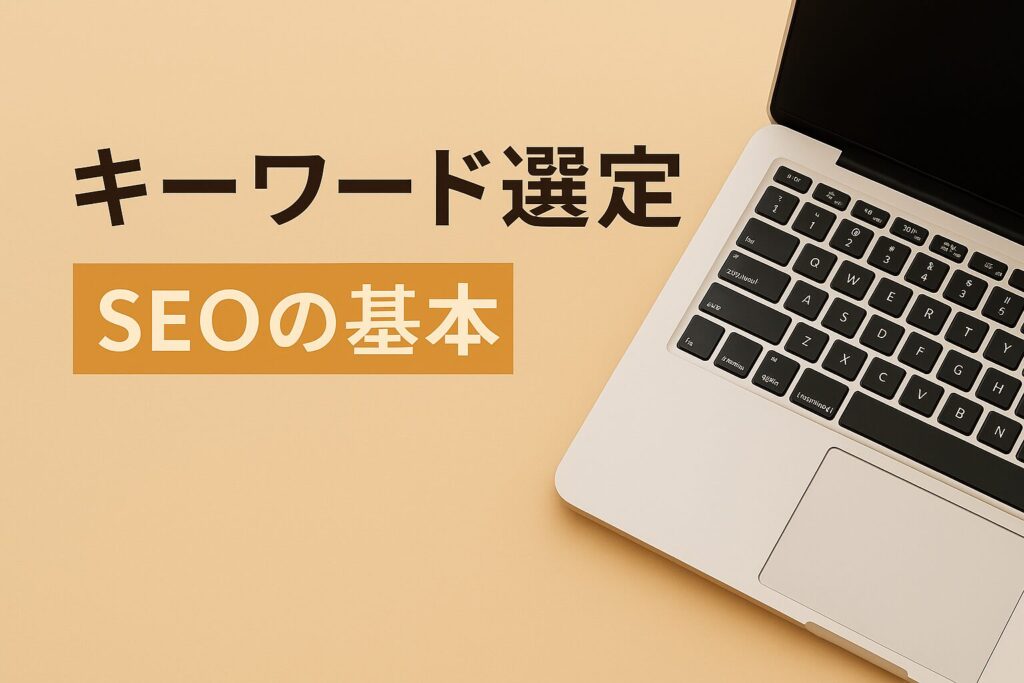 Wordpress
Wordpress 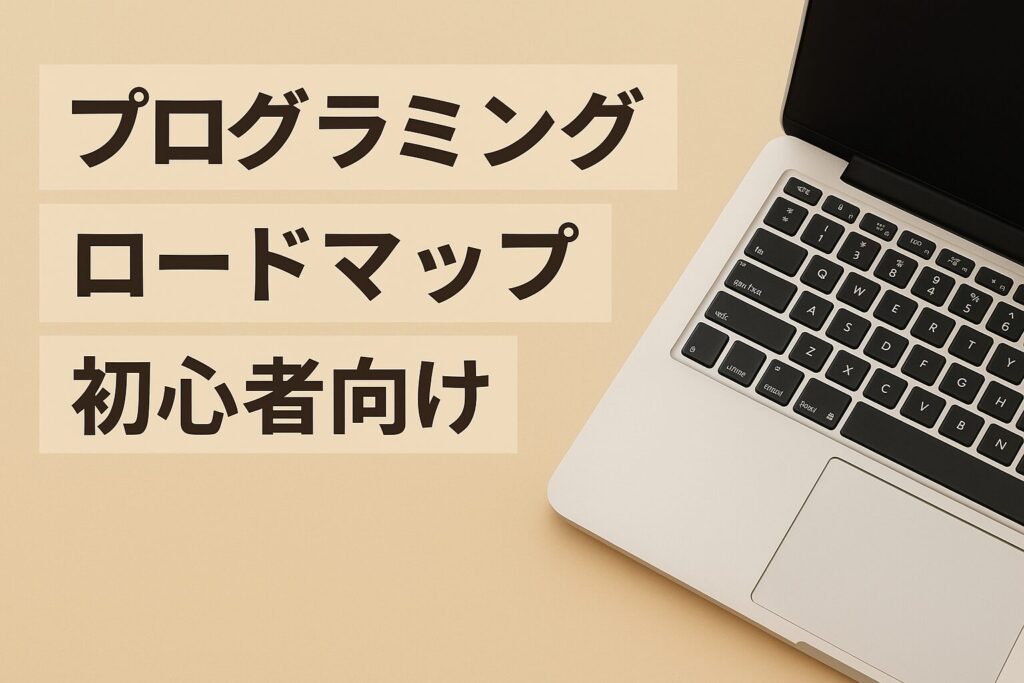 ロードマップ
ロードマップ  Spring Boot(Javaフレームワーク)
Spring Boot(Javaフレームワーク)